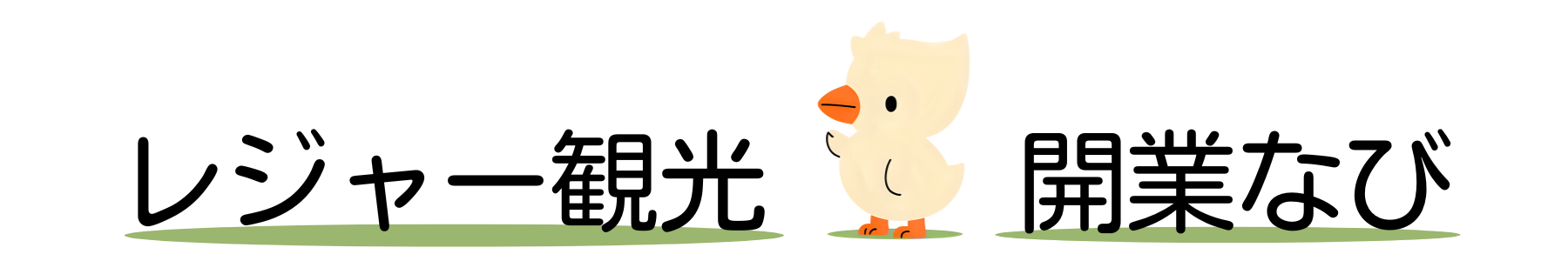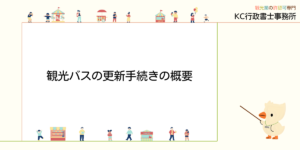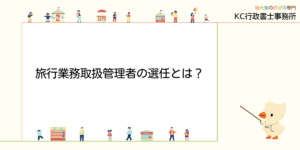各所の観光スポットまで送り迎えを行い、同時に観光案内もする観光タクシー。観光業の中でも比較的自由に稼働できるため、個人開業に興味がある方もいるのではないでしょうか。
しかし、観光タクシーは観光案内をメインにしたとしても、タクシーと同等のサービスを提供しているため、タクシーの営業に必要な一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得しなければ営業できません。この許可を取得するためには様々な要件を満たさなければならず、開業ハードルが高いのが現実です。
一般乗用旅客自動車運送事業許可とは?
タクシー事業者になるためには、国土交通大臣より一般旅客自動車運送事業の許可を受けなければならないと道路運送法第四条により定められています。
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
道路運送法第4条
一般旅客自動車運送事業は一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業・一般乗用旅客自動車運送事業の3つに分けられています。一般乗合旅客自動車運送事業とは、個々の旅客の依頼に応じて運賃を収受し、自動車で乗合旅客を運送する事業のことで、いわゆる路線バスを指します。一般貸切旅客自動車運送事業とは、乗車定員11人以上で自動車を貸し切って旅客を運送する事業のことで、一般的に貸切バス事業を指します。一般乗用旅客自動車運送事業とは、乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する事業のことで、タクシー事業はこれになります。
一般乗用旅客自動車運送事業のうち、許可を受けた個人のみが自動車を運転する場合は個人タクシー事業と呼ばれます。観光タクシー含むタクシー・ハイヤー業を個人で営むためには、この個人タクシー事業として許可を受ける必要があります。
法人タクシー事業者のタクシー運転手は運転業務に集中できますが、個人タクシー事業者は、タクシー運転手業務に加えて、運行管理や車両整備、財政管理など事業のすべてを自分自身で行わなければなりません。
個人タクシー事業者の許可を得る方法

個人タクシー事業者として許可を受けるために、通常は2つの方法があります。
①新規許可
営業する区域の運輸局で新規の申請を行い、許可を得る方法です。
個人タクシー事業を始める場合、まずは管轄の区域で新規許可を行っているかを確認する必要があります。というのは、タクシーの供給過剰によって発生する安全面や交通渋滞といった諸問題を防ぐため、エリアごとに営業できるタクシーの台数には制限が設けられています。地域によっては新規許可を行っていない場合もあり、そのような地域で開業を目指す場合には②譲渡譲受を検討します。
②譲渡譲受
個人タクシーの許可を受けている事業者から事業を受け継ぐという方法です。
高齢等の理由で事業の廃業を検討している事業者を譲渡人として、譲渡人と譲受人の間で契約を締結し、管轄の運輸局が認可することで開業できるようになります。現在では譲渡譲受によって個人タクシー事業を開始する方が多くなっています。ただし、譲渡譲受の場合にも事業者が満たすべき基本的な要件は新規許可と変わりません。
申請において満たすべき要件
個人タクシー事業者になるために満たすべき要件は管轄の運輸局によっても異なりますが、関東運輸局の場合、主に以下を満たす必要があります。
| 項目 | 満たすべき条件 |
|---|---|
| 年齢 | 申請日時点で65歳未満 |
| 運転経歴 | タクシー又はハイヤー運転手としての経験が10年以上(年齢により異なる) |
| 法令遵守状況 | 申請前5年間で道路交通法などの違反による一定の処分を受けていない |
| 資金計画 | 設備資金、運転資金、車庫に要する資金、保険料を賄える自己資金の保有 |
| 設備状況 | 営業所、車庫、事業用自動車について適切な権限を有している |
| 健康状態 | 個人タクシーの営業に支障がない健康状態 |
| 運転適性 | 個人タクシーの営業に支障がない状態 |
| 法令知識 | 関東運輸局長が実施する法令の試験に合格した者 |
上記のように気軽に参入できる事業ではないことは明らかですが、特に運転経歴が高いハードルとなります。年齢により必要年数に違いはあるものの、タクシー運転手として10年以上の経歴がなければ要件を満たすことはできません。
その他にも事業運営に必要な自己資金の保有や、事業者として適切な法令知識の有するため法令試験に合格する必要があるなど、長期的な計画でないと開業できないのが個人タクシー事業の特徴です。一方で、参入障壁が高いため、観光タクシーとして適切な接客スキルや差別化を図ることで、目標を実現しやすい分野であるとも言えるでしょう。