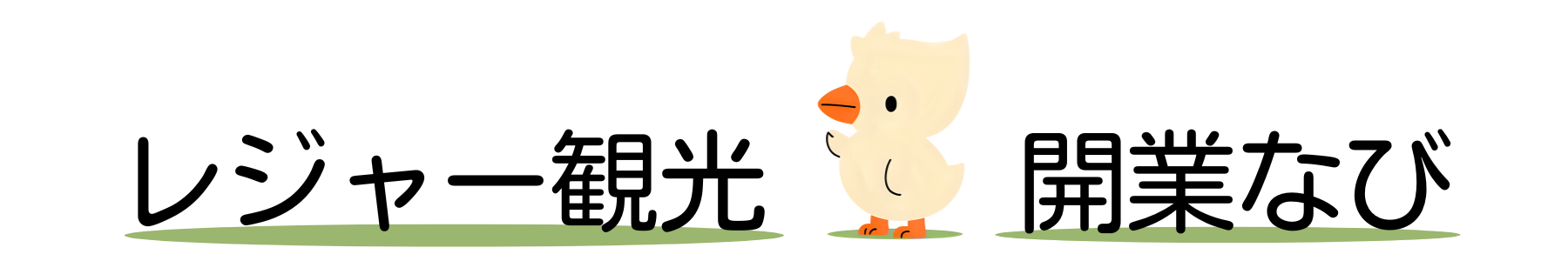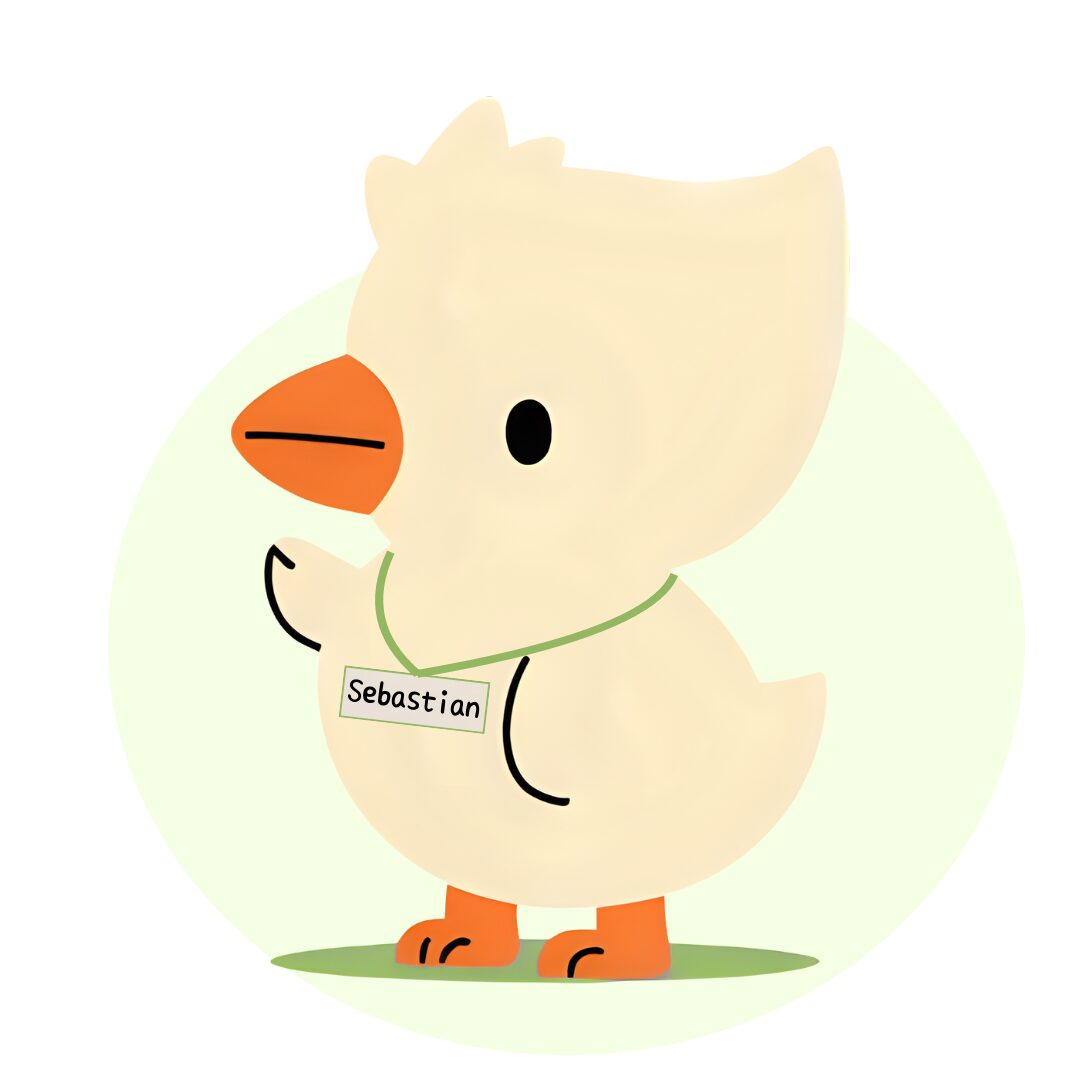 助手セバスチャン
助手セバスチャン不動産サイトを見ていると、「キャンプ場跡地」という物件を見かけるようになりました。キャンプ場って簡単に開業できるんですか?



そうですね。開業後の収益性などはさておき、ただ営業を始めるだけならば、他のビジネスに比べると難しくはありません。しかし、気を付けなければならない点もいくつかあります。
昨今のキャンプブームを受け、全国的にキャンプ場は非常に増えました。一方で、不動産ポータルサイトなどを見ているとキャンプ場跡地と思われる物件が売りに出されるのをちらほらと見かけるようになり、ブームとしての需要もひと段落落ち着いてきているのを感じます。
何かの事業を始める際には、収支計画や人員計画・サービス計画など、考えなければならないことは山ほどありますが、中でも重要である一方でわかり辛いのが「営業許可(ライセンス)」に関わる部分です。
キャンプ場という業態自体が宿泊や飲食など複数種のサービス提供を行う複合的な業種であり、キャンプ場開発も一種の施設開発にあたるため、営業する場所(土地)の法規制も絡むため、単純そうに見えて意外と複雑なのがキャンプ場の許認可です。



色々考えなきゃいけないことが多いのか…頭が痛くなってきた…



大丈夫です、基本から説明します。キャンプ場として営業を始めるためには、どんな許可が必要になるのかを見ていきましょう!
「キャンプ場」という営業許可は法律上存在しない


まず結論から言うと、「キャンプ場」という営業許可は法律上は存在しません。(自治体の条例等で存在する可能性はあります)
前述したとおり、キャンプ場は様々なサービスを組み合わせた複合的な業態です。寝泊まりする場所の提供、飲食物の提供、場合によっては体験アクティビティなども行うかもしれません。
そのため、営業許可をクリアするためには、提供するサービスを1つずつ切り分け、その行為それぞれに関わる許認可を整理して考える必要があります。よってどんなキャンプ場を営業するのか・どんなサービスを提供するのかにより必要な許認可は変わってきますが、まず基本的に知っておくべき許可の種類は3つあります。人を宿泊させる際に必要になる「旅館業営業許可」飲食物を提供する際に必要になる「飲食営業許可」お酒を販売する際に必要になる「酒類販売業免許」です。
ここからはそれぞれの許可について、キャンプ場の営業とどう絡んでくるのかを詳しく見ていきましょう。
旅館業営業許可
旅館業営業許可とは、ホテルや旅館など宿泊施設に必要な許認可で、法律上は「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」をする際に必要になる許可として定義づけられます。
2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
旅館業法第2条より
3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
つまり、キャンプ場を営業する際においても、「①施設を設け②宿泊料を受けて③人を宿泊させる」という3つの条件に該当する場合には旅館業営業許可が必要になります。
一般的に、キャンプ場の営業が旅館業に該当するか否かを判断する際は、「施設を設け」るかどうかが問題となります。「施設を設け」とは、法律の条文を読み解いていくと「常設の施設に寝具等を配置して人が寝泊まりできる空間を提供する行為」として解釈できます。
よって、ただ単にキャンプする場所を提供し、お客さんが自分で持ってきたテントを張って寝泊まりするいわゆる「オートキャンプ場」のような形態であれば旅館業の許可は不要なのが一般的な見解です。(駐車場のような場所貸しと同様の営業形態と捉えることができます)
ただし、近年急速に広がりを見せたグランピングテント(ドームテント)やトレーラーハウスのような業態の場合、常設の施設に寝具を置く「施設を設け」に該当すると考えられるので、旅館業の営業許可が必要となるのが一般的です。
なお、グランピングテントやトレーラーハウスを設置する前にはこれらが「建築物」に該当するのかどうか、旅館業とは別途、自治体の管轄課に協議する必要があります。(もし建築物であるという判断を受けた場合は更に規制法令は増えることになりますが、これは営業許可とはまた別のお話です。詳しくは以下の記事をご覧ください。)


飲食営業許可
キャンプ場を営業する際には、併設で飲食売店を設けたり、あるいはお客さんがバーベキューを手ぶらで楽しめるように食材の提供を計画することもあると思います。飲食物の提供を行うために必要な許認可が食品衛生法に基づく飲食営業許可です。
食材の仕込みや調理といった行為には許可が必要になるので、調理場の構造基準など一定の基準を満たした上で検査を受けて飲食営業許可を受ける必要があります。
ただ、飲食営業許可についてもどんな行為を行うかによって許可が必要か否かは変わってくるので、例えば自ら調理をするようなことはせず、冷凍品を仕入れて保管し受け渡しを行うだけの場合などは届出だけで済む場合もあります。
また、スナックやペットボトル飲料など常温で長期間の保存しても腐敗など食品衛生上の危害発生の恐れのない食品の販売には届出も必要ありません。
酒類販売業免許
「酒類販売業」と聞くとお酒を提供する場合には必須と思いがちですが、実はこちらもその行為の内容によって変わってきます。
例えば、バーなどのように、ビアサーバーを設置してそこからグラスなどに注いだビールを提供する場合、前述の飲食営業許可により営業が可能となります。
つまり一般的な居酒屋やレストラン同様に酒類販売業免許は必要としません。(これは酒類販売業の根拠法令となる「酒税法」で、「酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については」適用外とされているからです。)
一方、冷蔵庫などで缶や瓶ビールを保管しておいてそれをそのまま販売する、という方法によって提供を行う場合は、酒類販売業免許が必要になります。酒類販売業免許は「酒税法」という法律に基づいた許認可となっており、食品衛生法の営業許可とは性質が異なります。食品衛生法が食中毒など食品事故を防ぎ食品の安全性を守るための法律であるのに対し、酒税法はその名の通りお酒の税金の徴収に関する事項を定めた法律です。
酒税販売業免許を取得するためには、経営基礎要件など、旅館業や飲食営業とは異なる要件が求められます。
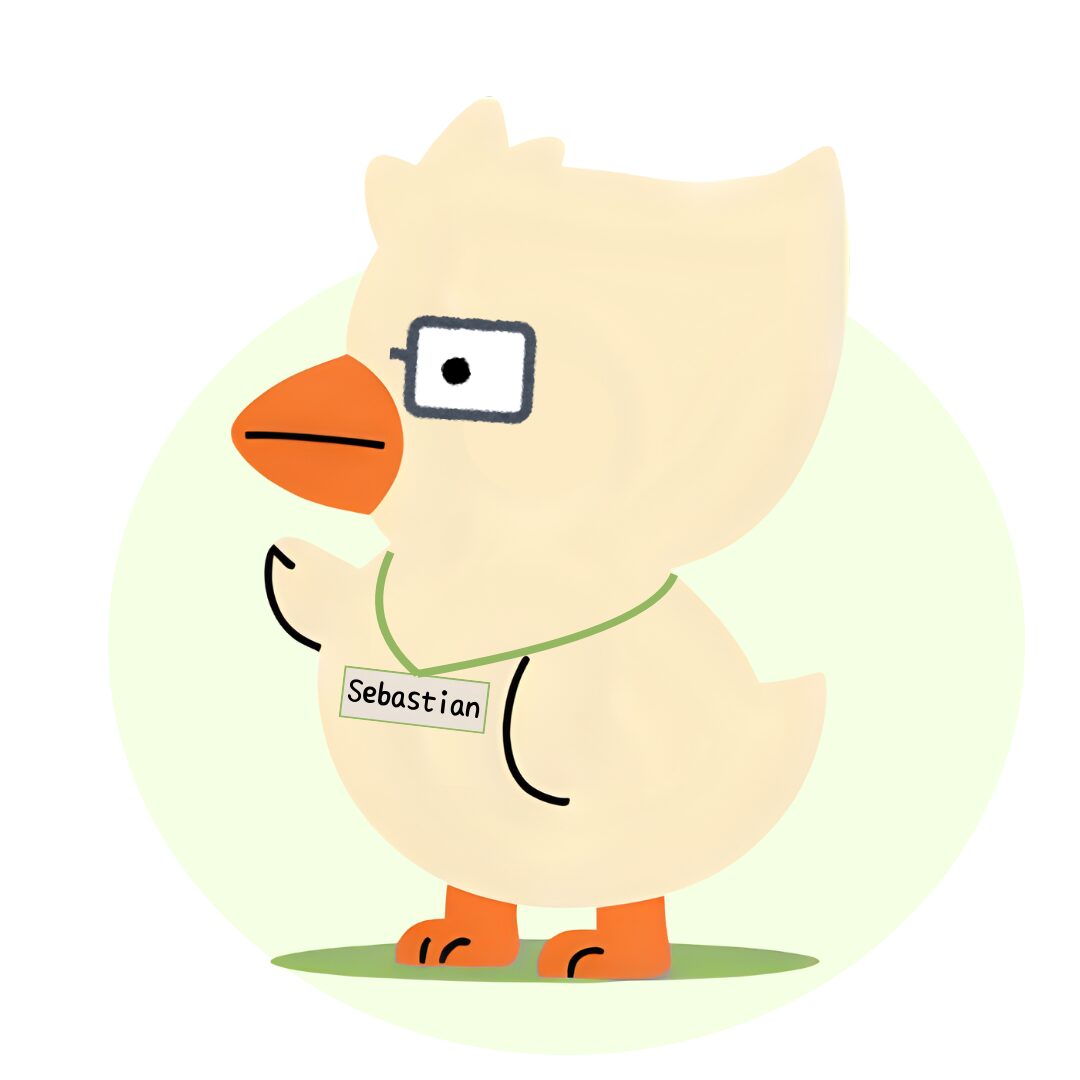
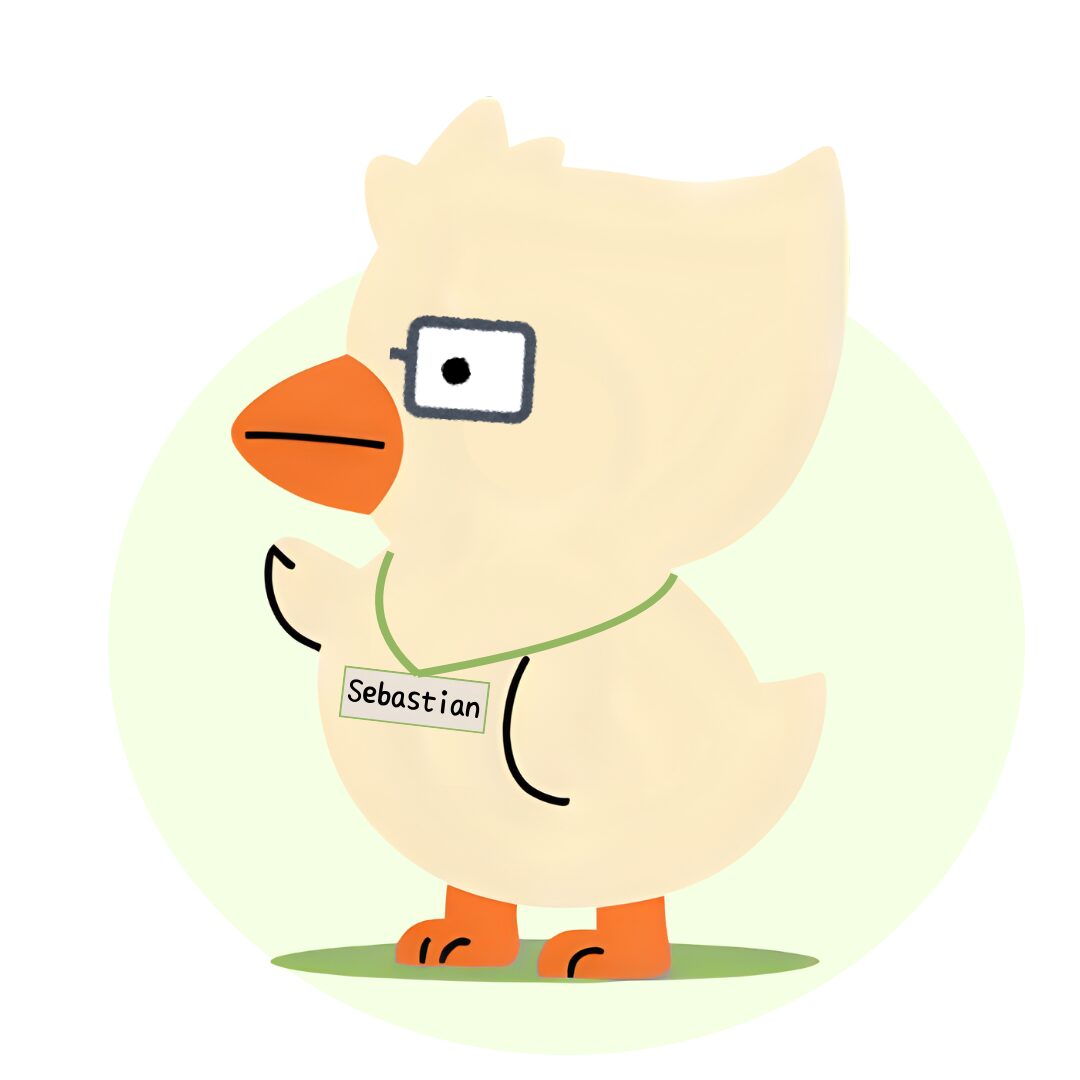
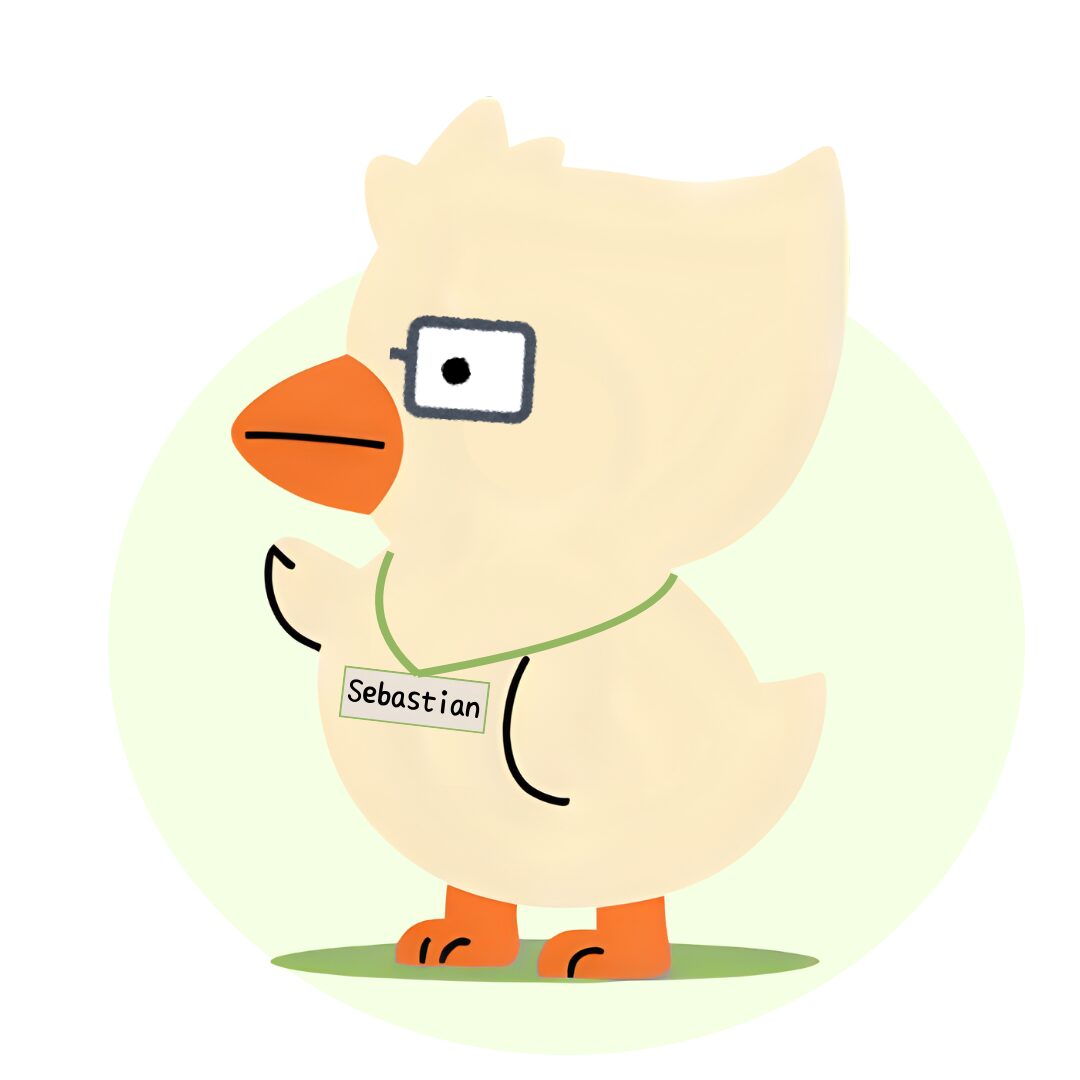
なるほど…つまり、キャンプ場でどんなサービスを提供したいのかによって、必要な許可は変わってくるということですね!



その通りです!まずは自分がキャンプ場でどんな事業展開をしたいのか、青写真を描くところから始めてみましょう!
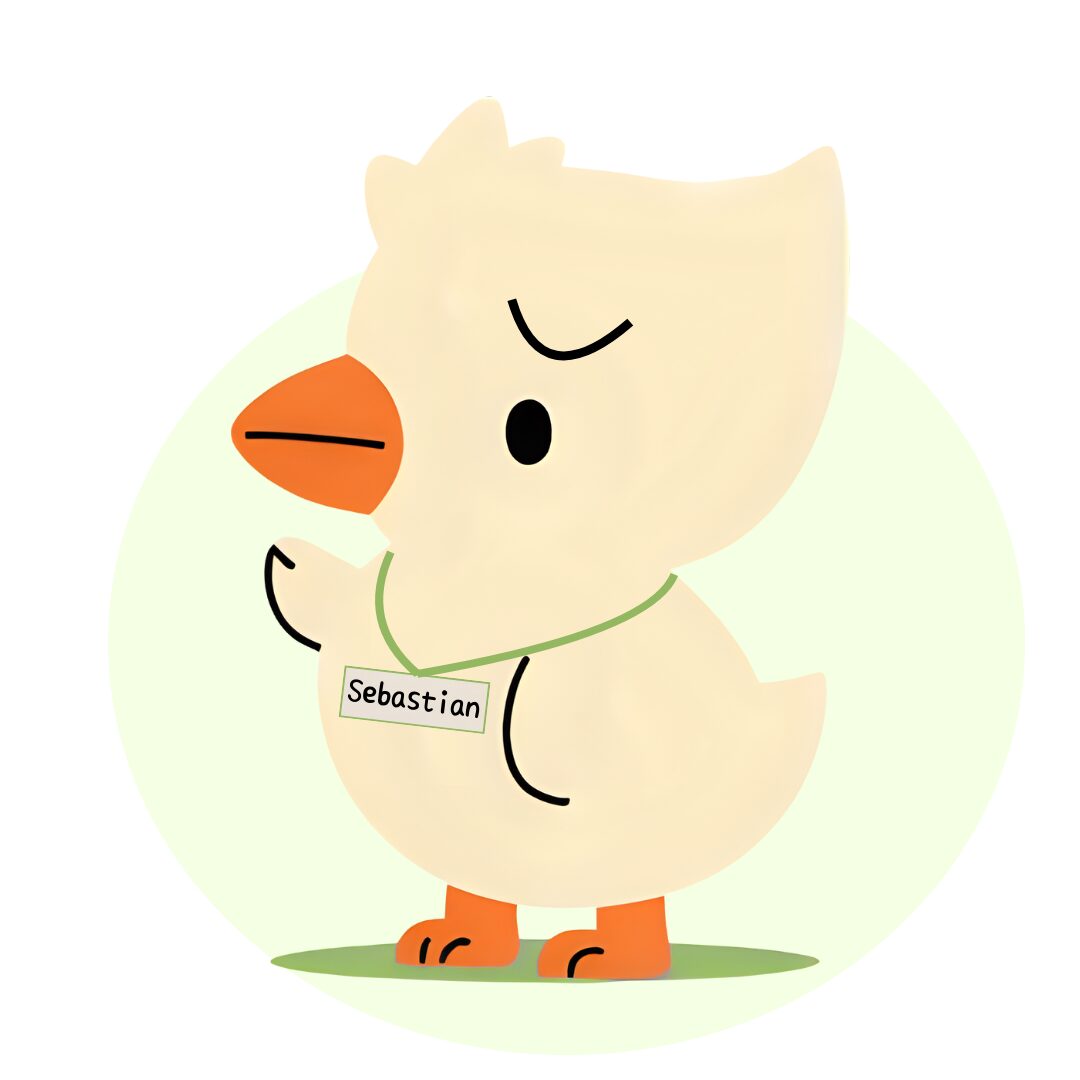
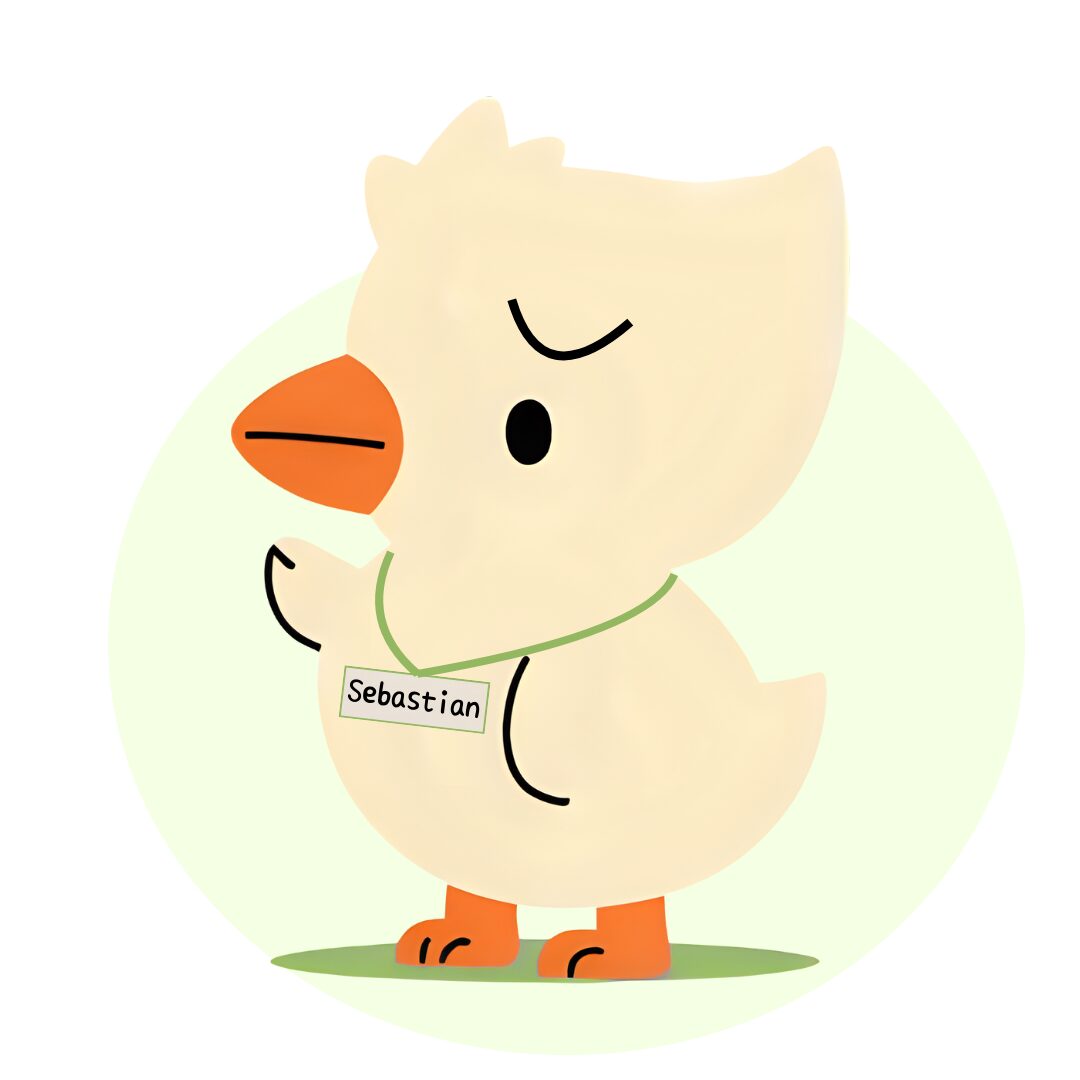
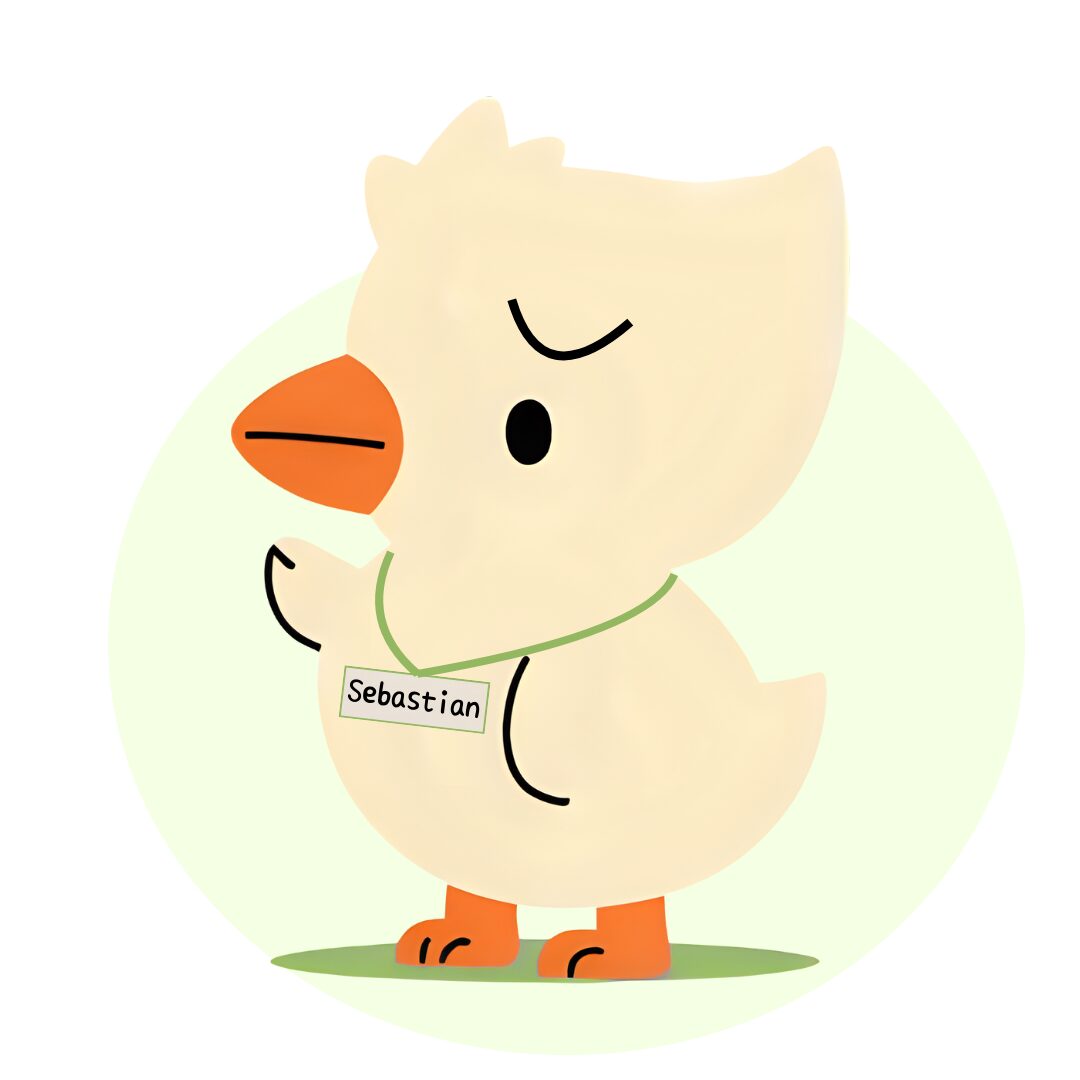
…青写真ってなんですか?