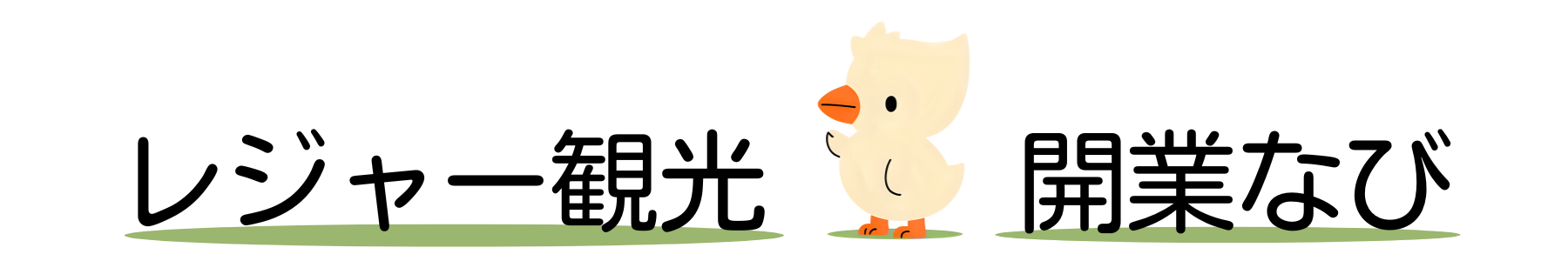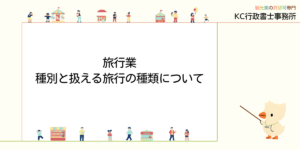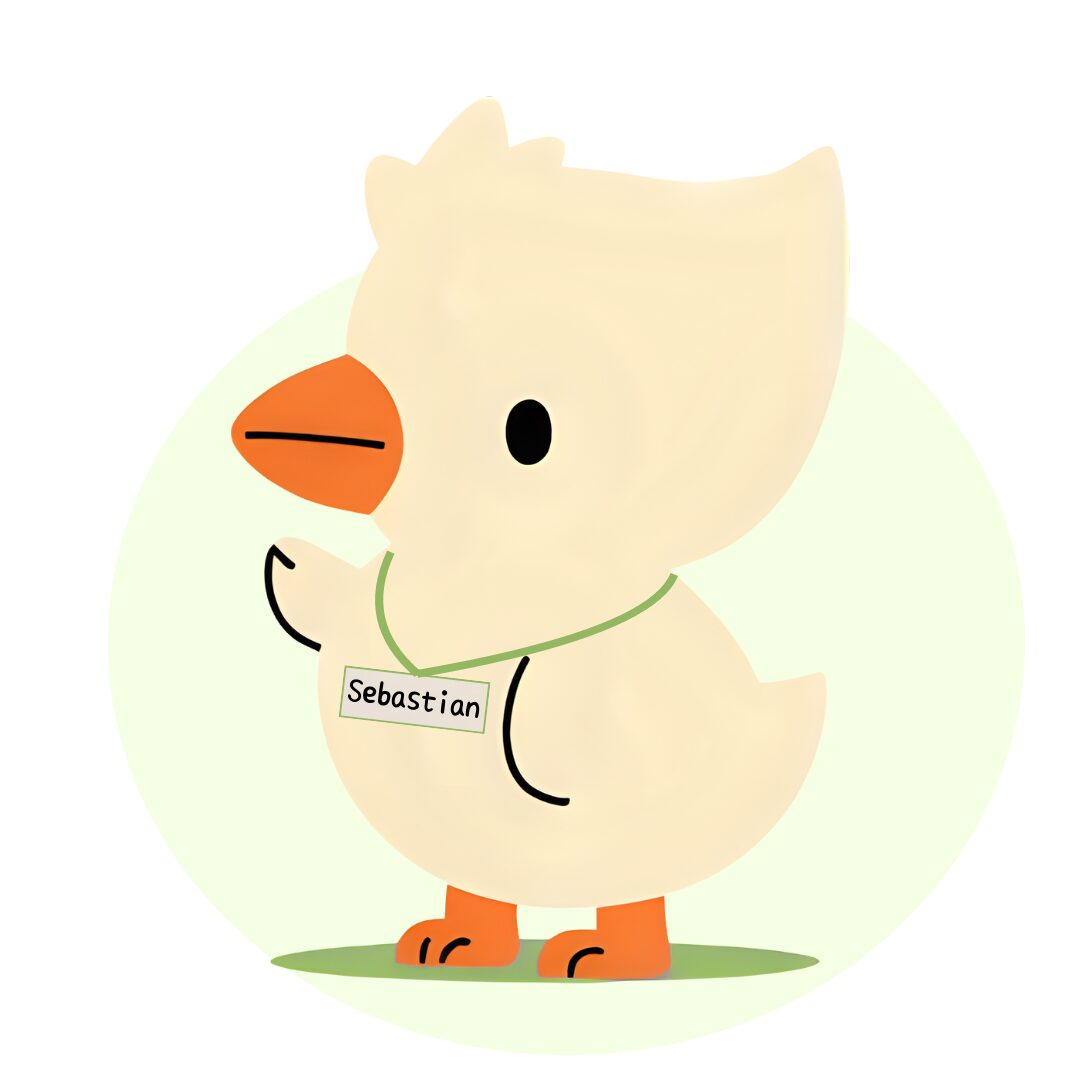 助手セバスチャン
助手セバスチャン今度開業するカフェで地元のクラフトビールを販売したいんです。何か許可は必要ですか?



それは素敵な取り組みですね。僕も飲みに行きますね。
クラフトビールを瓶や缶で物販として売る場合には酒類小売業免許を受けなければなりません。カフェでドリンクの1種として提供する場合は食品営業許可の範囲内として可能です。
レジャーや観光のお供に欠かせないお酒。私も観光地やレジャー施設に訪れるとビールや地酒なんかが売っているとテンション上がってついつい飲んでしまいます。
お酒の販売にあたっては許認可が必要となり、様々な要件を満たさなければならないためあらかじめ計画に盛り込んで事業準備を進める必要があります。



まずはお酒を販売・提供するための許認可制度について把握していきましょう。
お酒を提供するために必要な許認可は2つにわかれる


お酒を提供する際に必要な許認可は、基本的にはその提供の態様によって2通りにわかれます。
お酒をジョッキなどに注いて提供する場合は食品営業許可、お酒を缶や瓶のまま提供する場合は一般酒類小売業免許が必要となります。
一般酒類小売業免許とは、スーパーやコンビニなどお酒を消費者に販売(小売り)する際に必要となる免許です。酒税法という法律に基づいており、この免許を取得することで原則としてすべての品目の酒類を販売できることになります。
一方、食品営業許可は食品衛生法に基づいて飲食店を営む際に必要となる許可です。食品営業許可を取得して飲食店などを営む場合には、その許可でお酒も提供できるので、一般酒類小売業免許は必要ありません。
(酒類の販売業免許)
酒税法第9条
第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
このように、酒税法では、居酒屋やレストランがその場で飲むためにお酒を提供する場合には酒類販売免許が不要になる、ということが規定されています。
逆に言うと、テイクアウトなどその営業場以外で飲用に供される場合には酒類販売免許が必要になります。
まずは食品営業許可でお酒を提供することを検討


2つの許認可について説明しましたが、どちらの許認可の取得を検討していけばいいでしょうか。
もちろんどのような事業を行いたいかによって選定していくべき、ということは大前提として、あくまで許認可の面で言うと、飲食営業許可を取得しその範囲内でお酒を提供することを考える事業者が多いです。
これには食品営業許可よりも一般酒類小売業免許の方が要件が厳しく、そもそも一般酒類小売業免許の取得に必要な要件を満たせないケースがあるという背景があります。
一般酒類小売業免許を取得するためには、販売所の構造的な要件を満たさなければならないほか、申請者の酒類小売業への従事経験が3年以上必要になります(他の事業の経営経験で代替できる場合もあります)。いきなり免許を取得するにはややハードルが高いのです。



セバスチャンはライブハウスでお酒を飲んだことはありますか?
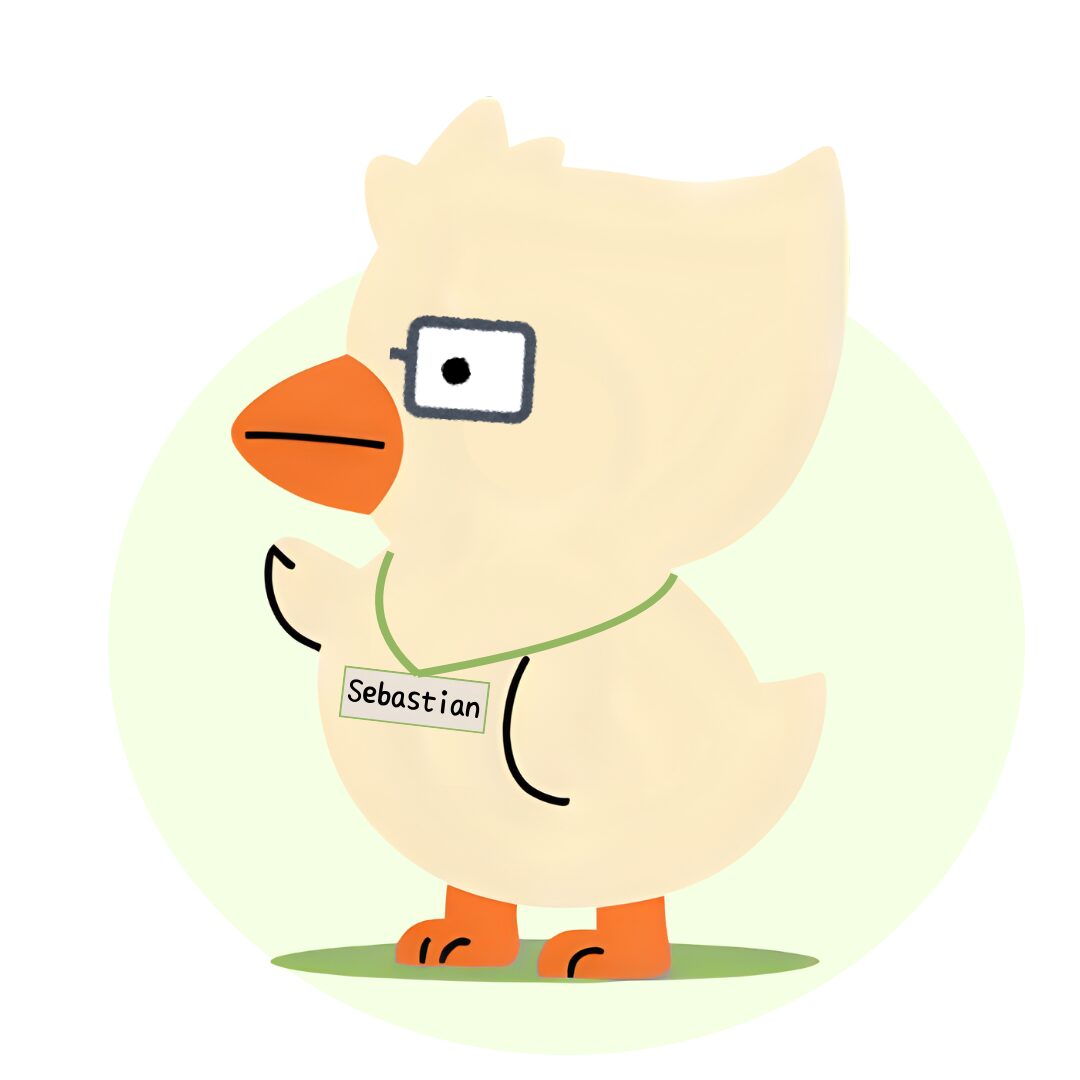
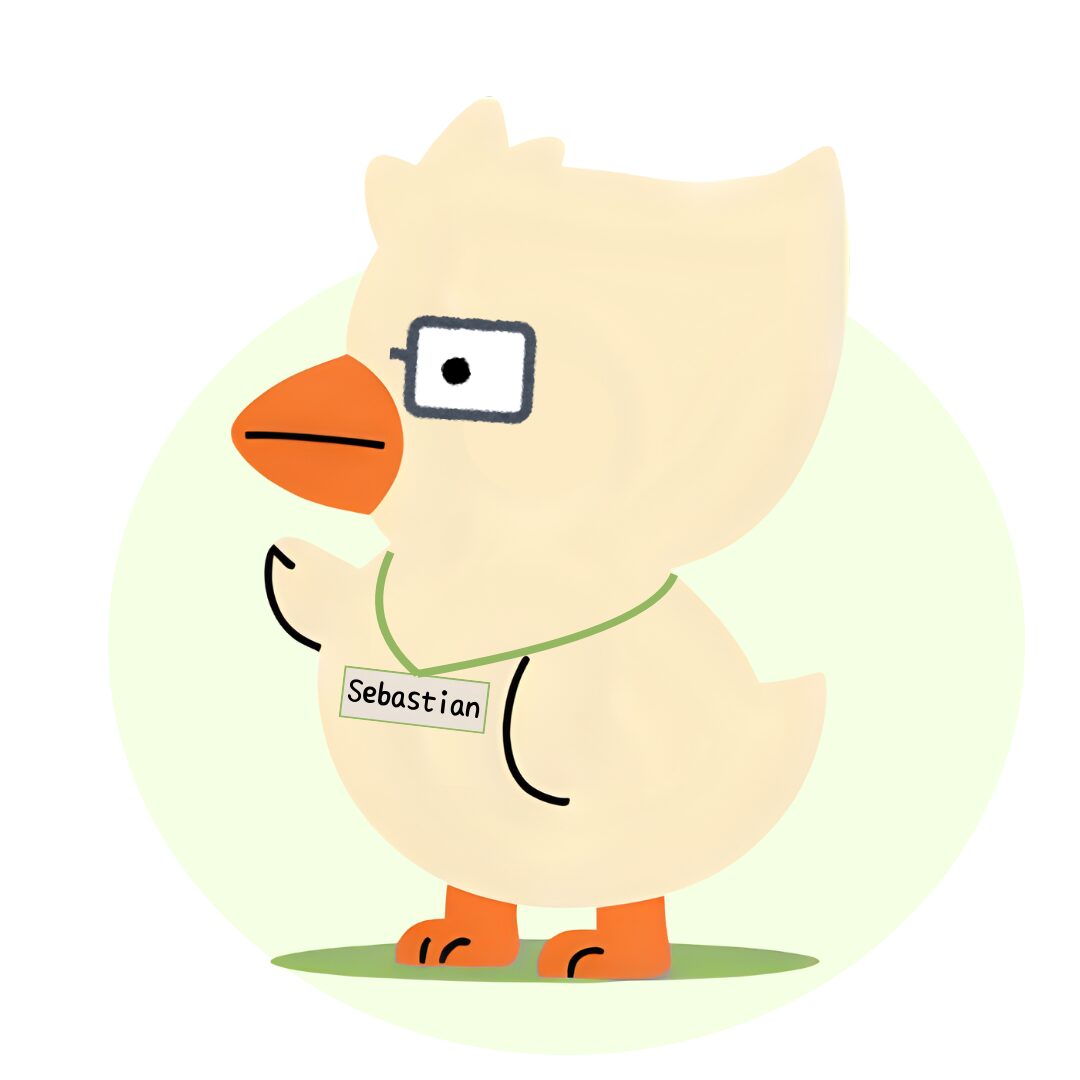
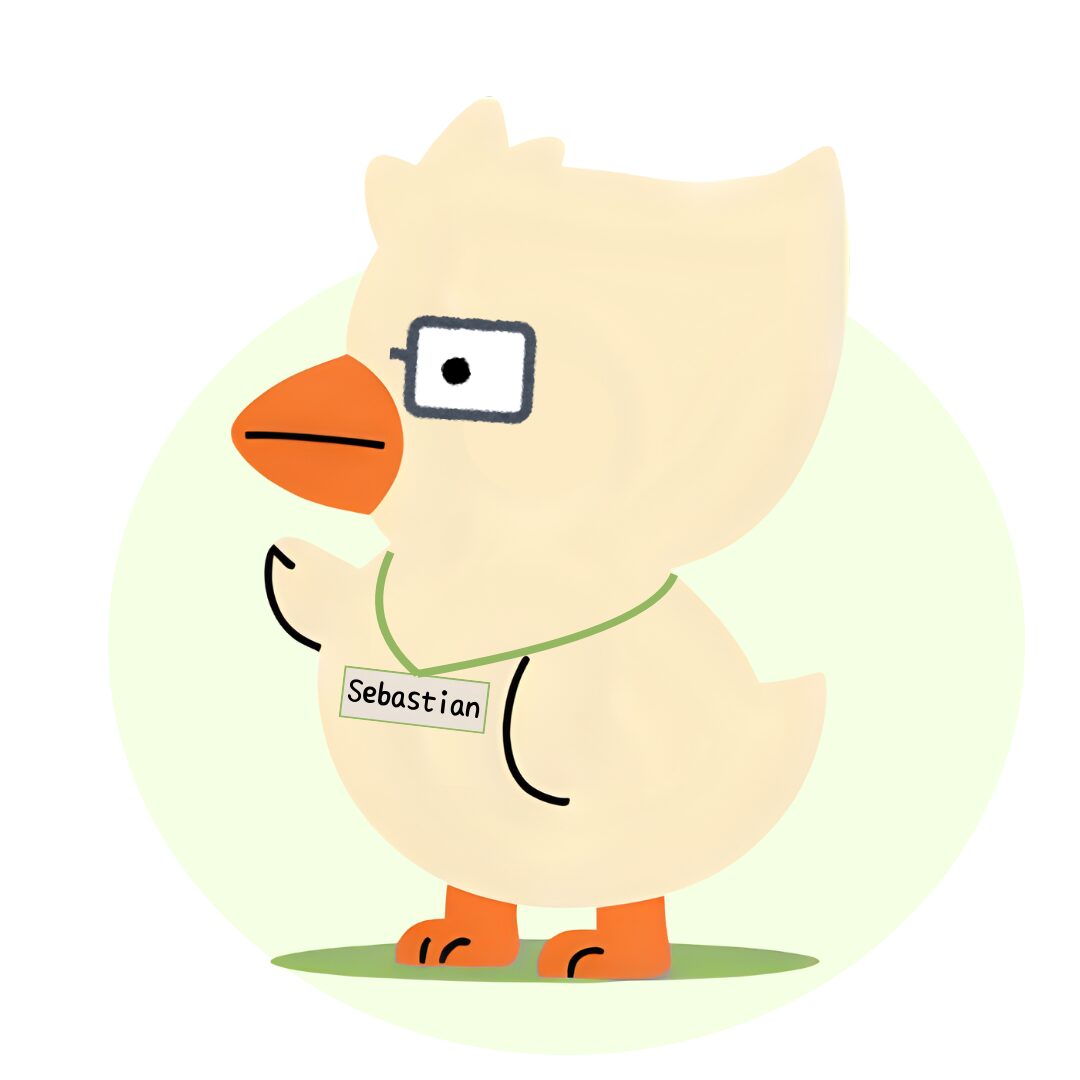
ライブハウスのドリンク受け取り所でビールを頼むと、開栓した状態で渡されますよね。



これも酒類販売免許ではなく食品営業許可の範囲内で提供を行うためという、許認可の背景があります。