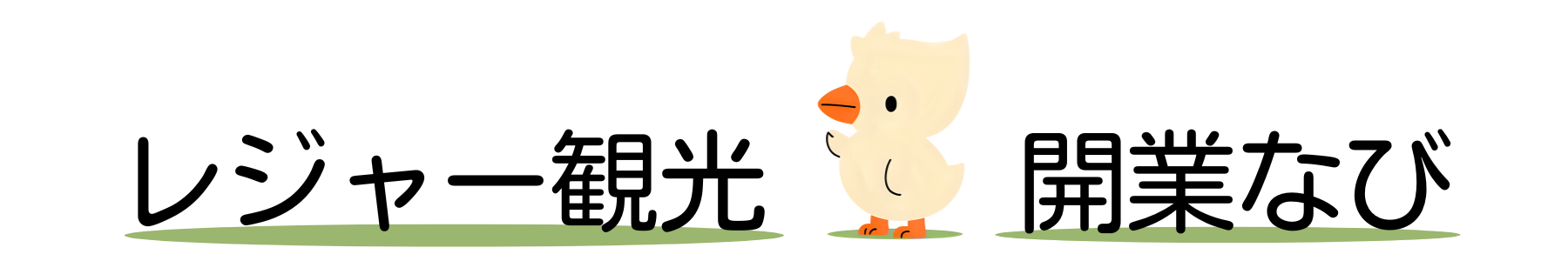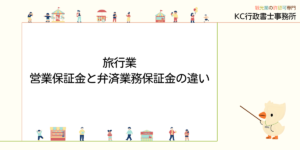助手セバスチャン
助手セバスチャンカフェの開業に向けて準備しているのですが、ハサップがよくわかりません…



ハサップは結局何をしたらいいのか分からないという人が多いです。
制度概要から対応手順まで解説しますので、一緒に確認していきましょう。
食品衛生法に基づき許可の申請や届出を行う場合に対応を求められるHACCP。
HACCP(ハサップ)は、簡単に言うと、飲食店を含む原則すべての食品事業者が遵守しなければならない衛生管理の基準です。食品衛生法に定められた義務のため、食品を扱う事業者(食品の製造・加工、調理、販売を含む)はHACCPの制度を理解した上で必要な措置を実施していかなければなりません。
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)は「ハサップ」と読み、「危害要因分析重点管理点」と訳されます。食品の製造~提供までの工程別に危害要因を把握・分析し、管理や記録・改善の体制を構築することで、食品の安全性の向上を図り食品事故のリスクを低減する役割を持ちます。
元々は国際的な基準で、日本では2020年施行の食品衛生法改正を機にすべての食品等事業者において義務化されました。
事業者の規模によって対応事項は異なる
すべての食品等事業者が対象となっていますが、事業者の規模によって対応すべき事項は異なっています。
具体的には、従業員50名以上の大規模事業者と50名未満の小規模事業者にわけられ、大規模事業者については事業者自らHACCPに基づいて一からその管理計画を作成し衛生管理を行わなければならない一方で、小規模事業者は既存の手引書を参考に簡略化されたアプローチで衛生管理を行います。
小規模事業者のHACCPの対応事項
ここからは小規模事業者のHACCP対応について詳しく見ていきましょう。
業界団体が作成し厚生労働省が内容を確認した手引書を参考に、以下の項目を実施する必要があります。まずは自分の業種・業態が属する業界団体の作成した手引書をこちらから探しましょう(厚生労働省のページに飛びます)。
そして手引書を確認しながら以下の流れで衛生管理を実施します。
手引書の解説を読み、自分の業種・業態では何が危害要因となるかを理解する
手引書のひな型を利用して、衛生管理計画と手順書を準備する
内容を従業員に周知する
手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録する
手引書で推奨された期間、記録を保存する
記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す
大切なのは、手引書を通じて自身の業態の衛生リスクを理解し、それを従業員に周知・徹底するということです。そのために手順書の作成や実施状況の記録が必要になります。
具体的な対応事項例
とはいえいまいち「一体何をしたらいいのか」イメージしづらいと思います。そこで、手引書の通読を行ったあとに行うべき対応例を紹介します。
手順書の作成
手引書に手順書のひな型が記載されているので、これを自分の運営に即した形に修正していきましょう。例えば小規模な一般飲食店の手引書では、以下の項目についての衛生管理の手順を記載することとしています。
- 原材料の受入の確認
- 冷蔵、冷凍庫の温度確認
- 交差汚染、二次汚染の防止
- 器具等の洗浄、消毒、殺菌
- トイレの洗浄、消毒
- 従業員の健康管理、衛生的作業着の着用など
- 衛生的な手洗いの実施
- 温度計の点検
管理表の作成
手順書と併せて実施記録の管理表も作成していきます。
管理表の作成例も手引書にのっており、基本的に手順書に対応した内容になっています。
小規模な一般飲食店の場合、衛生管理が手順書通りになされているか、毎日〇×をつけていったり、冷蔵庫や冷凍庫の庫内温度の記録などを行う内容となっています。
実施と記録
上記の内容をを従業員に共有していきます。手順書と管理表を併せて説明するのがわかりやすいでしょう。
従業員は共有を元に日々の業務中に記録をしていきます。この記録を定期的に振り返り、問題点の把握や改善を検討します。
記録は一定期間保管しておきます。例えば小規模な一般飲食店の手引書では1年程度の保管を推奨しています。
万が一問題が発生した場合には危害要因の特定につながると共に、顧客や保健所に対して適切に衛生管理を行っていたことの証拠書類となります。
HACCPへの対応が必要ない業種
公衆衛生に与える影響が少ない(=食品衛生上のリスクが低い)営業として規定される以下の業種はHACCPへの対応(衛生管理計画・手順書の作成)は不要とされています。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗など食品衛生上のリスクがない包装食品の販売業
- 器具容器包装の輸入また販売業
- 1回の提供食数が20食程度未満の施設
- 農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調製等)
HACCPで衛生管理を徹底する
以上がHACCPの概要と実際に実施すべき事項の流れです。
事業者にとっては利益に貢献する内容ではないため面倒に感じる方もいるかもしれませんが、食品は口にした人の健康に直結するため、衛生管理の徹底が非常に大切です。これを実現するためのHACCPという制度ですから、万が一の食品事故を防ぐために、適切な制度実施に努めましょう。
※なお、HACCPへの対応は食品衛生法に定められた義務です。努力義務ではありません。
第五十条 厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。
食品衛生法第50条
② 営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。)は、前項の規定により基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。